
【 フルフェイスカバー付き 帽子 】 アウトドア 農作業 ガーデニング用 紫外線カット 通気性良好メッシュ素材 超軽量 速乾 ネイビー 濃紺色
夜に受け取って色はブラックでは?思い朝太陽光で再度ネイビーであることを確信しました。
作りは想像どおり。正面のカバーは使うことは無いと思いますが全体的に納得です。
気が付いた点は
・色が違う
・サイズ調整用の後ろの止め具が効かないのでズルズルと伸びてくる(とめ方を自分なりに変更してクリア)
後は大丈夫。結構気に入ったので星4個にしておきました。
作りは想像どおり。正面のカバーは使うことは無いと思いますが全体的に納得です。
気が付いた点は
・色が違う
・サイズ調整用の後ろの止め具が効かないのでズルズルと伸びてくる(とめ方を自分なりに変更してクリア)
後は大丈夫。結構気に入ったので星4個にしておきました。

のぶカンタービレ! 全盲で生まれた息子・伸行がプロのピアニストになるまで
私がこのピアニストを知ったのはとあるニュース番組でのことだった。それ以前にも新聞のコンサート欄で彼の名前を見聞きしてはいたが、その当時は彼のことを全く知らずにいた。
「ハンディキャップ」との言葉を感じさせない軽やかで素直なピアノ演奏が強く印象に残り、間もなくしてから彼のデビューCDを購入することとなった。
日本での「ハンディキャップがある」という言葉からは得てしてマイナスのイメージがつきがちだが、アメリカを始め殊にヨーロッパでは逆にプラスのイメージに理解される場合が多い。その背景として日本の社会風土では「ハンディ・障害者=普通とは異なる=社会的弱者」との認識が一般に定着してしまっていることがある。
逆に外国では「ハンディキャップ」を一つの個性として理解する。それは一人一人の人間が持つ感性や好みと同レベルといっても過言ではない。一人一人の意見や物の考え方が異なるのは当たり前とするのはヨーロッパの社会が古くはゲルマンの大移動で形成されたように多言語・多人種で構築されてきたことに起因するのかもしれない。使う言葉が異なれば何とかしてコミュニケーションをとろうとして真剣に相手と向き合う。相手の社会生活を知ろうとすれば何とかして社会的な立場を越えようとする。そして理解し合えた時には互いにハグする。
自らの目の前にいるのは自らと同じ人間なのだ、決して猛獣やエイリアンの類ではない。少しだけ違う文化や形を持って生活しているだけに過ぎない。
少なくとも教育の世界で大切なことは“相手の持つ最大の魅力”を如何に引き出して伸ばすことが出来るか、だと思う。けれど残念ながら学校の先生方は忙しい。授業や学級経営よりも事務的な仕事や雑務に時間を奪われて子供に接する時間はほんの僅か、というのが現実でもある。
この意味で教師だけでなく子供に接する全ての人、例えば親やスポーツ教室のコーチなども本来は「教育者」なのである。子供が10人いたら子供に接する人はそれぞれ10ずつの引き出しを持つことが必要となり、自らも学ぶことを求められる。なかでも子供にとっての親は最も身近にいる「オーダーメイドのコンシェルジェ」なのである。
真剣に向き合うことで子供は変わる。誰にも一つは他の人より秀でた部分が必ずある。自らの才能に気付かせることで“学ぶ歓び”を知り、今度は自身がその能力を発揮することで他の人と歓びを分かち合おうとする。
辻井さんがこれまで歩んできた人生の軌跡に触れたことで、それもごく一端にすぎないかもしれないが、辻井さんと共に歩んできたコンシェルジェの方々の姿を見て、相手と自然にそして真剣に向き合う時に初めて本質的な意味での教育が始まる、と改めて考えさせられる一書だった。
デビューしてからほぼ2年の月日が過ぎ、辻井さんも一人の大人として自立し始めた。
いつの日にかこの国が様々な形の教育コンシェルジェの方々とそのサービスを受ける子供達の眩しい笑顔で一杯になる日が訪れるように今から種を蒔いていけば、この国の溶融にストップをかけるには未だ間に合うかもしれない。個人的には仕事が忙しくても1日に一度は必ず子供と話しをする。それも聞き役に徹していこうと思う。
仕事の帰りに新作を買って帰り、子供と一緒に聴くこととしよう。
「ハンディキャップ」との言葉を感じさせない軽やかで素直なピアノ演奏が強く印象に残り、間もなくしてから彼のデビューCDを購入することとなった。
日本での「ハンディキャップがある」という言葉からは得てしてマイナスのイメージがつきがちだが、アメリカを始め殊にヨーロッパでは逆にプラスのイメージに理解される場合が多い。その背景として日本の社会風土では「ハンディ・障害者=普通とは異なる=社会的弱者」との認識が一般に定着してしまっていることがある。
逆に外国では「ハンディキャップ」を一つの個性として理解する。それは一人一人の人間が持つ感性や好みと同レベルといっても過言ではない。一人一人の意見や物の考え方が異なるのは当たり前とするのはヨーロッパの社会が古くはゲルマンの大移動で形成されたように多言語・多人種で構築されてきたことに起因するのかもしれない。使う言葉が異なれば何とかしてコミュニケーションをとろうとして真剣に相手と向き合う。相手の社会生活を知ろうとすれば何とかして社会的な立場を越えようとする。そして理解し合えた時には互いにハグする。
自らの目の前にいるのは自らと同じ人間なのだ、決して猛獣やエイリアンの類ではない。少しだけ違う文化や形を持って生活しているだけに過ぎない。
少なくとも教育の世界で大切なことは“相手の持つ最大の魅力”を如何に引き出して伸ばすことが出来るか、だと思う。けれど残念ながら学校の先生方は忙しい。授業や学級経営よりも事務的な仕事や雑務に時間を奪われて子供に接する時間はほんの僅か、というのが現実でもある。
この意味で教師だけでなく子供に接する全ての人、例えば親やスポーツ教室のコーチなども本来は「教育者」なのである。子供が10人いたら子供に接する人はそれぞれ10ずつの引き出しを持つことが必要となり、自らも学ぶことを求められる。なかでも子供にとっての親は最も身近にいる「オーダーメイドのコンシェルジェ」なのである。
真剣に向き合うことで子供は変わる。誰にも一つは他の人より秀でた部分が必ずある。自らの才能に気付かせることで“学ぶ歓び”を知り、今度は自身がその能力を発揮することで他の人と歓びを分かち合おうとする。
辻井さんがこれまで歩んできた人生の軌跡に触れたことで、それもごく一端にすぎないかもしれないが、辻井さんと共に歩んできたコンシェルジェの方々の姿を見て、相手と自然にそして真剣に向き合う時に初めて本質的な意味での教育が始まる、と改めて考えさせられる一書だった。
デビューしてからほぼ2年の月日が過ぎ、辻井さんも一人の大人として自立し始めた。
いつの日にかこの国が様々な形の教育コンシェルジェの方々とそのサービスを受ける子供達の眩しい笑顔で一杯になる日が訪れるように今から種を蒔いていけば、この国の溶融にストップをかけるには未だ間に合うかもしれない。個人的には仕事が忙しくても1日に一度は必ず子供と話しをする。それも聞き役に徹していこうと思う。
仕事の帰りに新作を買って帰り、子供と一緒に聴くこととしよう。
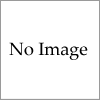
息子の部屋【字幕版】 [VHS]
大切な人の死は、どのように乗り越えられるのか。
そんなことを考えさせられる作品です。
たとえば、ラストシーンの海辺では、息子の死後、父が初めて笑う。
そのとき、父の心の中で初めて息子が「死んだ」。
つまり、遺族にとって、「死」は医療科学の判断で一義的に規定出来るものでもないし、信仰によっても、癒され得ない。
時間をかけて、彼らの心や記憶のなかでゆっくり「死んでゆく」のでしょう。
監督の、そんな死生観を感じます。
また、「死」を一般化して語ることは危険で、つねに誰かの「死」はその遺族や知人を含む個別の出来事でしかありえない、というメッセージも読み取れます。
たとえば信仰、あるいは科学や論理的分析、精神分析(主人公は精神科医)で語られる「死」一般は!!有効か?
それらは、元気に生きている人間の論理ではないか。
身近な人の死を前にして、科学も信仰も何もしてくれないのではないか。
遺族同士や仲間との感情のシェアの中で、少しずつ昇華してゆくものではないか。
そんなメッセージです。
この映画ではさらに、その「一般化の危険性」が他のシーンでも描き出されます。
たとえば、主人公の精神科医と常連の患者の会話。(趣旨のみ再現)
「私はしばらく休業するから、他の医者を紹介するよ」
「いや、あなたの所に通院してるんだ。他じゃダメです」
つまり、精神科医“一般”に通院するのではない。個別の○○先生に通院するというわけです。
つまり、危機や哀しみに直面したとき、抽象的な「生/死」一般、「医師/患者」一般などを対象にし!て!、語れるのか。
そんな問題を観る者に問うてきます。
そんなことを考えさせられる作品です。
たとえば、ラストシーンの海辺では、息子の死後、父が初めて笑う。
そのとき、父の心の中で初めて息子が「死んだ」。
つまり、遺族にとって、「死」は医療科学の判断で一義的に規定出来るものでもないし、信仰によっても、癒され得ない。
時間をかけて、彼らの心や記憶のなかでゆっくり「死んでゆく」のでしょう。
監督の、そんな死生観を感じます。
また、「死」を一般化して語ることは危険で、つねに誰かの「死」はその遺族や知人を含む個別の出来事でしかありえない、というメッセージも読み取れます。
たとえば信仰、あるいは科学や論理的分析、精神分析(主人公は精神科医)で語られる「死」一般は!!有効か?
それらは、元気に生きている人間の論理ではないか。
身近な人の死を前にして、科学も信仰も何もしてくれないのではないか。
遺族同士や仲間との感情のシェアの中で、少しずつ昇華してゆくものではないか。
そんなメッセージです。
この映画ではさらに、その「一般化の危険性」が他のシーンでも描き出されます。
たとえば、主人公の精神科医と常連の患者の会話。(趣旨のみ再現)
「私はしばらく休業するから、他の医者を紹介するよ」
「いや、あなたの所に通院してるんだ。他じゃダメです」
つまり、精神科医“一般”に通院するのではない。個別の○○先生に通院するというわけです。
つまり、危機や哀しみに直面したとき、抽象的な「生/死」一般、「医師/患者」一般などを対象にし!て!、語れるのか。
そんな問題を観る者に問うてきます。





