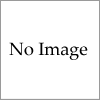
ハヴ・ユー・ハード:ジム・クロウチ・ライブ [DVD]
やっと日本版が出ました 以前だったら動くジム・クロウチなんてなかなかおがめませんでしたが、ばっちりLIVE癒されます! 息子のA.J.クロウチが語り、彼の暖かい人柄がジンワリ伝わって来る暖かいLIVEです!モーリー・ミューライゼンとのデュオは絶妙で、二人の間に「愛」を感じてしまう位ほんとに絶妙な間合いでギター&ハーモニーが・・・素晴らしい! 涙・涙・・・あぁ もぅこのデュオを観てるだけでも癒されます、もぅ曲目についてはあえて言いません(リージョン1のレビューの方々に同感)、何しろ動く映像が観れるってだけでも感動なんですから・・・ ゲスト・トークにロギンズ&メッシーナとかランディ・ニューマンなどのコメントがあるので私なんかは字幕のある日本版の方が楽しめました!
余談ですが、最近 これに近い感覚で、久しぶりにあったかいLIVEを演奏する若手で デパペペ の二人に同じ様なものを感じました!
余談ですが、最近 これに近い感覚で、久しぶりにあったかいLIVEを演奏する若手で デパペペ の二人に同じ様なものを感じました!

ヴェリー・ベスト・オブ
タランティーノの「ジャンゴ繋がれざる者」を見て、この映画の中で最高に素晴らしいシーンである、クリストフ・ヴァルツ とジェイミー・フォックスがタッグを組んで雪山を馬で走るシーンのバックに、なんと「アイ・ガッタ・ネーム」が使用されていて、それは新鮮な驚きでした。
この映画、マカロニウェスタンの名曲が何曲も使われたりしていて、タランティーノが好きな映画音楽を集めちゃったという感じで、映画ファンには嬉しいばかりでしたが、「アイ・ガッタ・ネーム」も「ラスト・アメリカン・ヒーロー」のテーマ曲。
シ゜ム・クロウチといえば高校生の頃に「オペレーター」とか「リロイ・プラウンは悪い奴」などがよくラジオから流れ、アコースティックギターのフレーズがとてもカッコ良く、楽譜を手に入れたかったけど、どこにもなかった記憶があります。
そして「アイ・ガッタ・ネイム」の発売日に飛行機事故でなくなってしまって、それから記憶からもだんだんに消えかかっていたのですが、タランティーノがジム・クロウチを忘れるなよ、とばかり映画の最高のシーンで使ってくれました。
改めてベストアルバムを聞き直して、やっぱりギターのフレーズがかっこ良くて、最高です。タランティーノ、ありがとう。
この映画、マカロニウェスタンの名曲が何曲も使われたりしていて、タランティーノが好きな映画音楽を集めちゃったという感じで、映画ファンには嬉しいばかりでしたが、「アイ・ガッタ・ネーム」も「ラスト・アメリカン・ヒーロー」のテーマ曲。
シ゜ム・クロウチといえば高校生の頃に「オペレーター」とか「リロイ・プラウンは悪い奴」などがよくラジオから流れ、アコースティックギターのフレーズがとてもカッコ良く、楽譜を手に入れたかったけど、どこにもなかった記憶があります。
そして「アイ・ガッタ・ネイム」の発売日に飛行機事故でなくなってしまって、それから記憶からもだんだんに消えかかっていたのですが、タランティーノがジム・クロウチを忘れるなよ、とばかり映画の最高のシーンで使ってくれました。
改めてベストアルバムを聞き直して、やっぱりギターのフレーズがかっこ良くて、最高です。タランティーノ、ありがとう。

Photographs & Memories
日本ではあまり想像できないが飛行機による移動中の事故で亡くなるケースがアメリカでは多いという。オーティス・レディングやレイナード・スキナードなど確率から考えると信じられない数のアーティストも惨禍に見舞われており、彼ジム・クロウチもそんな不幸に見舞われた一人だった。とりわけBad,Bad Leroy BrownのNo.1ヒットをはじめヒット曲を連発し始めた矢先の事故は成功との対比という点で最も悲劇的だったのではないだろうか。どうしてもその事を考えて聴いてしまわずにはいられないが、お茶目なストーリーテリングが楽しいtrack.1やtrack.10がそれを忘れさせてくれる。穏やかに淡々と歌われるtrack.2,3,9,11,12は聴くものの心を癒し、盟友モーリー・ミューライゼンとのアコースティックギター2本の絡みによる美しい響きに心洗われるようで今や彼のようなミュージシャンがいない事を考えると、悲劇の前にこれだけの楽曲が残された幸運を喜ぶべきなのかもしれない。
彼の死を悼むようにチャートを駆け上り1位に到達したTime In A Bottleには、偶然とは言え「過ぎ去る時を封印する願い」が祈るように歌われている。それはまるでこの作品集をはじめてとして彼の多くの歌声も同様に「ボトル」に封印される事を予感しているかのようでもあり、聴く度に琴線に触れる名曲だ。いろいろ編集盤が出ているようだが、「去りし男の伝説」の邦題でもリリースされていたこのコンピレーションがオススメです。
彼の死を悼むようにチャートを駆け上り1位に到達したTime In A Bottleには、偶然とは言え「過ぎ去る時を封印する願い」が祈るように歌われている。それはまるでこの作品集をはじめてとして彼の多くの歌声も同様に「ボトル」に封印される事を予感しているかのようでもあり、聴く度に琴線に触れる名曲だ。いろいろ編集盤が出ているようだが、「去りし男の伝説」の邦題でもリリースされていたこのコンピレーションがオススメです。

Original Albums...Plus
ジム・クロウチの代表作3枚「You Don't Mess Around With Jim」
「Life and Times」「I Got A Name」に、オリジナルアルバム未収録の
トラック(既発)をセットしたお得な2枚組。
今までジム・クロウチのCDアルバムをいろいろと購入してきたが、権利が乱れて
いる関係からか、様々なレーベルから乱発されており、音質もいまいち良くない
ものが多かった。
昔、ABCからアナログ盤として出ていた「グレイテスト・ヒッツ」は、現在、
アトランティック系のSAJAレーベルから発売されているが、これにはオリジナル・
マスターテープの表示が表記されており音質は良かった。
しかし、一枚ものベストでは、到底ジムの名曲の数々から考えても物足りず、これ
までに、オリジナル・アルバム体裁のもの(音質はイマイチ)や名もないレーベルの
数枚組みのベストなど、いろいろと購入してきた。
もともとアナログ盤で本来の音質がよく分かったいたため、どこのレーベルのCD
がオリジナル・マスターテープに一番近いのか、それが一番気になるところだった。
しかし、多くの再発物は残念なことに音質が良くなく、折角のジムのボーカルが
キンキンと響いたり、ギターがメタリックで耳についたり・・・と散々だった。
ところが、今回のエドセル盤はオリジナルマスター並(表示はされていないが
ひょっとするとオリジナル・マスターかも)の高音質で極めて良好。
全体的にボーカルや生ギターの音色が自然で、歪み感少なく安心して聞いていら
れる。私の大好きな曲「Recently」のモーリー・ミューライゼンのギターがとても
魅力的に鳴っている。やはり、音質は大切な要素であることを確認。久々にジムの
歌声に深く感動することができた。
ジャケットはカラー31ページの立派なもので、特筆すべきは何と全曲歌詞付き!
という豪華さ。さらに曲毎に参加ミュージシャンの記載もあり、50曲も収録され、
しかも驚くべき低価格で入手できるので、絶対のお薦め盤です。
オリジナル盤の再発(オリジナルマスター使用)を期待しつつ、このアルバムが
しばらくはメインになりそうです。
「Life and Times」「I Got A Name」に、オリジナルアルバム未収録の
トラック(既発)をセットしたお得な2枚組。
今までジム・クロウチのCDアルバムをいろいろと購入してきたが、権利が乱れて
いる関係からか、様々なレーベルから乱発されており、音質もいまいち良くない
ものが多かった。
昔、ABCからアナログ盤として出ていた「グレイテスト・ヒッツ」は、現在、
アトランティック系のSAJAレーベルから発売されているが、これにはオリジナル・
マスターテープの表示が表記されており音質は良かった。
しかし、一枚ものベストでは、到底ジムの名曲の数々から考えても物足りず、これ
までに、オリジナル・アルバム体裁のもの(音質はイマイチ)や名もないレーベルの
数枚組みのベストなど、いろいろと購入してきた。
もともとアナログ盤で本来の音質がよく分かったいたため、どこのレーベルのCD
がオリジナル・マスターテープに一番近いのか、それが一番気になるところだった。
しかし、多くの再発物は残念なことに音質が良くなく、折角のジムのボーカルが
キンキンと響いたり、ギターがメタリックで耳についたり・・・と散々だった。
ところが、今回のエドセル盤はオリジナルマスター並(表示はされていないが
ひょっとするとオリジナル・マスターかも)の高音質で極めて良好。
全体的にボーカルや生ギターの音色が自然で、歪み感少なく安心して聞いていら
れる。私の大好きな曲「Recently」のモーリー・ミューライゼンのギターがとても
魅力的に鳴っている。やはり、音質は大切な要素であることを確認。久々にジムの
歌声に深く感動することができた。
ジャケットはカラー31ページの立派なもので、特筆すべきは何と全曲歌詞付き!
という豪華さ。さらに曲毎に参加ミュージシャンの記載もあり、50曲も収録され、
しかも驚くべき低価格で入手できるので、絶対のお薦め盤です。
オリジナル盤の再発(オリジナルマスター使用)を期待しつつ、このアルバムが
しばらくはメインになりそうです。

ラスト アメリカン ヒーロー [DVD]
筆者の少年時代のお気に入りだった米テレビドラマに『爆発!デューク(The Dukes of Hazzard)』がある。同じく大好きだった映画に『トランザム7000(Smokey and the Bandits)』も。
前者は、密造酒を作っているじいさまの孫たちが、愛称「リー将軍」の真っ赤なダッジ・チャージャーを駆って、おマヌケな保安官をからかいながら密造酒を運ぶ痛快ドラマ。後者は、このレビューをお読みの方々なら説明不要と思うが、州境を越えて大量のビールを運ぶトラック(アルコール類を、州境を越えて運搬するのは州によって違法)を、バート・レイノルズ運転するトランザムが、これまたお間抜けな保安官が運転するパトカーから「護衛」するという、運び屋のカーチェイス映画だ。
両者に共通する要素に「酒」「ちょっとした違法行為」「マヌケな保安官との追っかけっこ」&「南部」があるのだが、これはアメリカ南部人にとって、誇り高き(?)伝統文化なのだ。
アメリカの犯罪小説などを読んでいると、一度ならず「ムーンシャイン(密造酒)」という言葉に出くわした事があると思う。これは、夜の闇に乗じて月明かりのもとで醸造する、という意味でつけられた隠語。こうした自家製の密造酒というのは、南北戦争に負けてこの方、北部資本主義に対し敗残意識を背負いながら貧困に喘いでいた南部のプア・ホワイトにとって、大恐慌にして禁酒法時代だった1930年代、税金を取り立てられずに家族を養うための格好の収入源だったため、禁酒法時代が終わってからも綿々と続いた南部の文化なのである。
日本でも、輸入酒店のバーボンのコーナーを覗いてみれば、蜂蜜のビンのような容器に、ホワイト・リカーと呼ばれる透明な液体、手製っぽい素っ気ないラベルで「Shine on Georgia Moon」(ジョージアの月よ、照らしておくれ)と印刷されている、ジョークのような名前のコーン・ウィスキーが見つかるかもしれない。もちろんこれは密造酒などではないが(笑)、南部人のユーモアのセンスはもちろん、「ムーンシャイン」文化に対する誇りが感じられるとは思われないだろうか。
前置きが長くなってしまったが、本作『ラスト・アメリカン・ヒーロー』は、そうした密造酒の運び屋から伝説的なレーサーになった実在の人物、ロバート・グレン・ジョンソン・jr.=通称ジュニア・ジョンソンをモデルにした(ただし映画の中ではジュニア・ジャクソン)痛快作である。
【あらすじ】
ノース・カロライナの山間部に暮らすジャクソン一家。父(アート・ランド)は、「取締りの役人もオレの酒を飲んでいる」とうそぶく密造ウィスキー作りの名人。息子のジュニア・ジャクソン(ジェフ・ブリッジス)は、父の密造酒を夜陰に乗じて運搬するドライバー。その腕っ節と度胸で、いつもATF(アルコール・タバコ・銃器取締局)の役人をぶっちぎり。
ある時、蒸留施設が役人にガサ入れされ、父は1年の刑に。ジュニアは、一家の生活費を稼ぐため、自慢の運転技術を生かし、自らエンジンを組み立てて、ストック・カー・レースに出場する。恐れ知らずで自爆もいとわない走りっぷりで、ジュニアは次第に人気を高めていくが、その一方でブラックリストに上がってしまう。賞金目当てで始めたカーレースだったが、ジュニアはいつしかのめり込んでいく・・・。
田舎を舞台にしたカーチェイス映画が大好きな筆者は、前半の、土ぼこりを巻き上げてパトカーと追いかけっこを繰り広げる様がもう観ていて楽しくてしょうがないのだが、やがてジュニアがレースに魅せられて、ストック・カーの世界にはまり込んでいく後半も悪くない。このストック・カー・レースというのが実にワイルドなのだ。小突き合いに幅寄せ、クラッシュと、ナスティなことこの上ない。
さらに映画の中では、デモリション・ダービーというのが出てくるが、これは車同士をぶつけ合って、相手の車を破壊するとんでもない競技。最後に残った車が優勝という、アメリカでしかありえないような荒っぽいスポーツ(?)だ。
主人公のモデルになったジュニア・ジョンソンは恐れ知らずの運転で「ハード・チャージャー(飛ばし屋)」として名を馳せたレーサー。
このストック・カー・レースは「下層の人間がクズを集めてイキがっているだけのものだ」などと上流階級から叩かれた。「えてして車は中古車、観客席はガタガタの木造り。ドライバーはただの田舎者。彼らはレギュラー・ガソリンをそこまで持ち込んで、相手のタイヤをぶち破ったり、ボディをへこませたりと、マナーだって滅茶苦茶だった」(原作より)
それもそのはず、ストック・カー・レースはそもそも下層階級から始まったもの。ムーンシャイン・ランナーと呼ばれる田舎の若者たち、そして都市部の肉体労働者層たちが、自らスーパーチャージャーなどを搭載して改造した車を持ち寄って始めたアンダーグラウンド・カルチャーだったのだ。都市から離れた、だだっ広い土地に忽然とレーストラックが引かれ、「ごろつき軍団」扱いする当局の妨害などを尻目に大盛況、終わると元通りの何もない場所に戻っていたという。こうして'50年代前半には熱狂的支持者を増やしていき、ひとつのスポーツとして定着してしまった。
1周2〜5キロの楕円形のトラックを大パワーマシンで疾走する単純なレースで、スピードは最高時速300キロを超えることも珍しくない。インディの平均時速よりずっと速く、この「南部スタイル」というのは、とにかく度胸が必要なレースで、ハンパではないコーナーの攻め方に、北部人たちはビビりまくるという。
ちょっと面白い話に、朝鮮戦争の時に授与された78個の名誉勲章のうち32個は南部人、しかも皆アパラチア山近郊の出身者。NY、つまり大都市圏からはたったの3人で、しかもそのうち1人はやはりアパラチア山岳地帯の出身者だったという。ジュニアの出身地域の男たちには、生まれながらの勇猛果敢な資質があるようで、これはアパラチア山丘陵地帯に入植した、スコットランド系アイルランド人の血筋と関係があると言われている。
ストック・カー・レースは、ナイスガイと呼ばれる南部の男たちにとって「ちょとした荒々しさで旧支配階級制度の呪縛を解く、自由の象徴」だったのだ。
ジュニア・ジョンソンを主人公にした映画は、本作以前にロバート・ミッチャム主演で『サンダーロード』というタイトルのものがあるらしいが、残念ながら筆者は未見。
本作では、『ラスト・ショー』で一躍注目されたジェフ・ブリッジスがジュニアを演じ、スピード狂の南部の若者を実にワイルドに好演している。スポンサーづきのレーサーたちをあざ笑い、自分の流儀を貫くふてぶてしい「反抗」の若者像が実に爽快なのだが、これは実在のジュニア・ジョンソンの逸話にもあるので後ほど紹介したい。
共演は、兄をサポートする弟のウェイン・ジャクソンをゲイリー・ビジー(若い!)、父を演じるアート・ランドはミュージカルで鳴らしたベテラン俳優だが、彼の演じる父親が実にいい存在感を醸し出していて、ある意味一番印象に残ったキャラクターだった(笑)。また、非常に興味深かったのは、ジュニアが惹かれるヒロイン、マージ(ヴァレリー・ペリーン)の存在。モーテルの一室で愛し合っていると、とつぜんドアを開けて花形レーサーたちが入って来ようとして、ジュニアがとまどう場面がある。実は彼女、レース場からレース場へと流れてゆく、レーサー専門の娼婦なのである。いかにもアメリカらしいユニークで逞しいヒロインだ。
原作は、「クール・クールLSD交感テスト」や「ライトスタッフ」で知られる、'60年代ニュー・ジャーナリズムの旗手の一人、トム・ウルフが'65年にエスクァイア誌に寄稿したコラム「The Last American hero」。
ハンター・S・トンプソンのお仲間ジャーナリストだけあって、ジュニア・ジョンソンに会いたくてしょうがない著者が、ついに憧れのヒーローとご対面するその熱気が伝わってくるような極めて主観的な文体だ(笑)。
「僕を含む総勢1万7000人の人間が、いっせいに国道421号線を抜け、ストック・カー・レース場へと車をひた走りに走らせる・・・こんな日に、おとなしくしていろというのが、どだい無理だ」
映画の中では、アート・ランド演じるジュニアの父は、息子に「オレと同じようにムショの臭い飯をお前らには食わせたくない」と言うような、理想の父親像のように描かれているが、実在のジュニアは父の手伝いで14歳の時に初めて密造酒運びをやらされたらしい(苦笑)。
ジュニアは、レーサーとしての天賦の才を持っていたようで、密造酒運びをしていた時代に様々な運転テクニックを編み出した。中でも有名なのが、「ブートレッグ(密造酒)・ターン」で、これは猛スピード状態から車のケツをスリップさせて180度回転し、元来た道を逆走し、パトカーをまくテクニック、いわゆる「スピンターン」のことだが、これはジュニア・ジョンソンが開発した技だと言われている。本当なのだろうか!また、パトランプを仕込んで、警官隊に仲間と思わせておいてバリケードを突破するアイディアもジョンソンが考えたと言われている。
レーサーになってからも、前を走る車の後ろにぴったりつけることで空気抵抗がなくなるスリップ・ストリーム状態を、理屈ではなく本能的な勘で発見し「ドラフティング」と名づけたり、まさに生まれながらのレーサーといえる。
先ほどもちょっと触れたが、ジュニア・ジョンソン伝説の一つにこんな話がある。彼は'63年、NASCAR(National Association for Stock Car Auto Racing)主催のレースに、シヴォレーで出場していたのである。当時シェヴィは、ストック・カー・レースから引き上げていて、レーサーたちはフォード、マーキュリー、プリマス、ダッジなどに乗っていた。フォードやクライスラーからは多額のバックアップ資金が出ていたのだが、ジュニアは、そうしたデトロイトの自動車メーカー、つまり「北部」から一切の支援を受けずに、シェヴィ一台に賭けてレースに出場していた。南部人の誇り、「反逆のヒ−ロー」ジュニア・ジョンソンのシボレーが登場すると、嵐のような喝采が巻き起こったという。
映画の中でも、スポンサーの申し出を跳ねのけるジュニアの不敵な性格が描かれているが、とにかくメンテナンス費用などが馬鹿にならない世界。実在のジョンソンも、やがてはフォードのドライバーになるのだが、その時は本当に「身売り」するのかどうかで南部男たちの間で賭けが行われた、とまで言われている。
ムーンシャインのルーツをひもといていくと、18世紀にアパラチア山系に入植したスコットランド系アイルランド移民たちが始めたものらしい。穀物栽培に向かない痩せた土地だったため、人々はトウモロコシの栽培からウィスキー作りに転向したという。1791年に、ウィスキーに法外な税金が課せられ、これに猛反対する農民たちによって「ウィスキー一揆」が勃発。1万5000人の州軍隊によって鎮圧された。こうした歴史的背景から、大恐慌・禁酒法時代を経てアパラチア山脈一円はウィスキーの密造地帯となっていった。
最後に、色々調べていたら、「Junior Johnson's MIDNIGHT MOON」という名前のコーン・ウィスキーを発見。何とこれはジョンソン・ファミリーの密造酒のレシピを受け継いで作られているものだというのだ!もちろんジュニア・ジョンソンのお墨付きで。
日本にも輸入されているのだろうか・・・?こいつを一杯やりながら、『ラスト・アメリカン・ヒーロー』鑑賞、としゃれこみたいものだ。これぞ映画マニアの至福。クーッ!
前者は、密造酒を作っているじいさまの孫たちが、愛称「リー将軍」の真っ赤なダッジ・チャージャーを駆って、おマヌケな保安官をからかいながら密造酒を運ぶ痛快ドラマ。後者は、このレビューをお読みの方々なら説明不要と思うが、州境を越えて大量のビールを運ぶトラック(アルコール類を、州境を越えて運搬するのは州によって違法)を、バート・レイノルズ運転するトランザムが、これまたお間抜けな保安官が運転するパトカーから「護衛」するという、運び屋のカーチェイス映画だ。
両者に共通する要素に「酒」「ちょっとした違法行為」「マヌケな保安官との追っかけっこ」&「南部」があるのだが、これはアメリカ南部人にとって、誇り高き(?)伝統文化なのだ。
アメリカの犯罪小説などを読んでいると、一度ならず「ムーンシャイン(密造酒)」という言葉に出くわした事があると思う。これは、夜の闇に乗じて月明かりのもとで醸造する、という意味でつけられた隠語。こうした自家製の密造酒というのは、南北戦争に負けてこの方、北部資本主義に対し敗残意識を背負いながら貧困に喘いでいた南部のプア・ホワイトにとって、大恐慌にして禁酒法時代だった1930年代、税金を取り立てられずに家族を養うための格好の収入源だったため、禁酒法時代が終わってからも綿々と続いた南部の文化なのである。
日本でも、輸入酒店のバーボンのコーナーを覗いてみれば、蜂蜜のビンのような容器に、ホワイト・リカーと呼ばれる透明な液体、手製っぽい素っ気ないラベルで「Shine on Georgia Moon」(ジョージアの月よ、照らしておくれ)と印刷されている、ジョークのような名前のコーン・ウィスキーが見つかるかもしれない。もちろんこれは密造酒などではないが(笑)、南部人のユーモアのセンスはもちろん、「ムーンシャイン」文化に対する誇りが感じられるとは思われないだろうか。
前置きが長くなってしまったが、本作『ラスト・アメリカン・ヒーロー』は、そうした密造酒の運び屋から伝説的なレーサーになった実在の人物、ロバート・グレン・ジョンソン・jr.=通称ジュニア・ジョンソンをモデルにした(ただし映画の中ではジュニア・ジャクソン)痛快作である。
【あらすじ】
ノース・カロライナの山間部に暮らすジャクソン一家。父(アート・ランド)は、「取締りの役人もオレの酒を飲んでいる」とうそぶく密造ウィスキー作りの名人。息子のジュニア・ジャクソン(ジェフ・ブリッジス)は、父の密造酒を夜陰に乗じて運搬するドライバー。その腕っ節と度胸で、いつもATF(アルコール・タバコ・銃器取締局)の役人をぶっちぎり。
ある時、蒸留施設が役人にガサ入れされ、父は1年の刑に。ジュニアは、一家の生活費を稼ぐため、自慢の運転技術を生かし、自らエンジンを組み立てて、ストック・カー・レースに出場する。恐れ知らずで自爆もいとわない走りっぷりで、ジュニアは次第に人気を高めていくが、その一方でブラックリストに上がってしまう。賞金目当てで始めたカーレースだったが、ジュニアはいつしかのめり込んでいく・・・。
田舎を舞台にしたカーチェイス映画が大好きな筆者は、前半の、土ぼこりを巻き上げてパトカーと追いかけっこを繰り広げる様がもう観ていて楽しくてしょうがないのだが、やがてジュニアがレースに魅せられて、ストック・カーの世界にはまり込んでいく後半も悪くない。このストック・カー・レースというのが実にワイルドなのだ。小突き合いに幅寄せ、クラッシュと、ナスティなことこの上ない。
さらに映画の中では、デモリション・ダービーというのが出てくるが、これは車同士をぶつけ合って、相手の車を破壊するとんでもない競技。最後に残った車が優勝という、アメリカでしかありえないような荒っぽいスポーツ(?)だ。
主人公のモデルになったジュニア・ジョンソンは恐れ知らずの運転で「ハード・チャージャー(飛ばし屋)」として名を馳せたレーサー。
このストック・カー・レースは「下層の人間がクズを集めてイキがっているだけのものだ」などと上流階級から叩かれた。「えてして車は中古車、観客席はガタガタの木造り。ドライバーはただの田舎者。彼らはレギュラー・ガソリンをそこまで持ち込んで、相手のタイヤをぶち破ったり、ボディをへこませたりと、マナーだって滅茶苦茶だった」(原作より)
それもそのはず、ストック・カー・レースはそもそも下層階級から始まったもの。ムーンシャイン・ランナーと呼ばれる田舎の若者たち、そして都市部の肉体労働者層たちが、自らスーパーチャージャーなどを搭載して改造した車を持ち寄って始めたアンダーグラウンド・カルチャーだったのだ。都市から離れた、だだっ広い土地に忽然とレーストラックが引かれ、「ごろつき軍団」扱いする当局の妨害などを尻目に大盛況、終わると元通りの何もない場所に戻っていたという。こうして'50年代前半には熱狂的支持者を増やしていき、ひとつのスポーツとして定着してしまった。
1周2〜5キロの楕円形のトラックを大パワーマシンで疾走する単純なレースで、スピードは最高時速300キロを超えることも珍しくない。インディの平均時速よりずっと速く、この「南部スタイル」というのは、とにかく度胸が必要なレースで、ハンパではないコーナーの攻め方に、北部人たちはビビりまくるという。
ちょっと面白い話に、朝鮮戦争の時に授与された78個の名誉勲章のうち32個は南部人、しかも皆アパラチア山近郊の出身者。NY、つまり大都市圏からはたったの3人で、しかもそのうち1人はやはりアパラチア山岳地帯の出身者だったという。ジュニアの出身地域の男たちには、生まれながらの勇猛果敢な資質があるようで、これはアパラチア山丘陵地帯に入植した、スコットランド系アイルランド人の血筋と関係があると言われている。
ストック・カー・レースは、ナイスガイと呼ばれる南部の男たちにとって「ちょとした荒々しさで旧支配階級制度の呪縛を解く、自由の象徴」だったのだ。
ジュニア・ジョンソンを主人公にした映画は、本作以前にロバート・ミッチャム主演で『サンダーロード』というタイトルのものがあるらしいが、残念ながら筆者は未見。
本作では、『ラスト・ショー』で一躍注目されたジェフ・ブリッジスがジュニアを演じ、スピード狂の南部の若者を実にワイルドに好演している。スポンサーづきのレーサーたちをあざ笑い、自分の流儀を貫くふてぶてしい「反抗」の若者像が実に爽快なのだが、これは実在のジュニア・ジョンソンの逸話にもあるので後ほど紹介したい。
共演は、兄をサポートする弟のウェイン・ジャクソンをゲイリー・ビジー(若い!)、父を演じるアート・ランドはミュージカルで鳴らしたベテラン俳優だが、彼の演じる父親が実にいい存在感を醸し出していて、ある意味一番印象に残ったキャラクターだった(笑)。また、非常に興味深かったのは、ジュニアが惹かれるヒロイン、マージ(ヴァレリー・ペリーン)の存在。モーテルの一室で愛し合っていると、とつぜんドアを開けて花形レーサーたちが入って来ようとして、ジュニアがとまどう場面がある。実は彼女、レース場からレース場へと流れてゆく、レーサー専門の娼婦なのである。いかにもアメリカらしいユニークで逞しいヒロインだ。
原作は、「クール・クールLSD交感テスト」や「ライトスタッフ」で知られる、'60年代ニュー・ジャーナリズムの旗手の一人、トム・ウルフが'65年にエスクァイア誌に寄稿したコラム「The Last American hero」。
ハンター・S・トンプソンのお仲間ジャーナリストだけあって、ジュニア・ジョンソンに会いたくてしょうがない著者が、ついに憧れのヒーローとご対面するその熱気が伝わってくるような極めて主観的な文体だ(笑)。
「僕を含む総勢1万7000人の人間が、いっせいに国道421号線を抜け、ストック・カー・レース場へと車をひた走りに走らせる・・・こんな日に、おとなしくしていろというのが、どだい無理だ」
映画の中では、アート・ランド演じるジュニアの父は、息子に「オレと同じようにムショの臭い飯をお前らには食わせたくない」と言うような、理想の父親像のように描かれているが、実在のジュニアは父の手伝いで14歳の時に初めて密造酒運びをやらされたらしい(苦笑)。
ジュニアは、レーサーとしての天賦の才を持っていたようで、密造酒運びをしていた時代に様々な運転テクニックを編み出した。中でも有名なのが、「ブートレッグ(密造酒)・ターン」で、これは猛スピード状態から車のケツをスリップさせて180度回転し、元来た道を逆走し、パトカーをまくテクニック、いわゆる「スピンターン」のことだが、これはジュニア・ジョンソンが開発した技だと言われている。本当なのだろうか!また、パトランプを仕込んで、警官隊に仲間と思わせておいてバリケードを突破するアイディアもジョンソンが考えたと言われている。
レーサーになってからも、前を走る車の後ろにぴったりつけることで空気抵抗がなくなるスリップ・ストリーム状態を、理屈ではなく本能的な勘で発見し「ドラフティング」と名づけたり、まさに生まれながらのレーサーといえる。
先ほどもちょっと触れたが、ジュニア・ジョンソン伝説の一つにこんな話がある。彼は'63年、NASCAR(National Association for Stock Car Auto Racing)主催のレースに、シヴォレーで出場していたのである。当時シェヴィは、ストック・カー・レースから引き上げていて、レーサーたちはフォード、マーキュリー、プリマス、ダッジなどに乗っていた。フォードやクライスラーからは多額のバックアップ資金が出ていたのだが、ジュニアは、そうしたデトロイトの自動車メーカー、つまり「北部」から一切の支援を受けずに、シェヴィ一台に賭けてレースに出場していた。南部人の誇り、「反逆のヒ−ロー」ジュニア・ジョンソンのシボレーが登場すると、嵐のような喝采が巻き起こったという。
映画の中でも、スポンサーの申し出を跳ねのけるジュニアの不敵な性格が描かれているが、とにかくメンテナンス費用などが馬鹿にならない世界。実在のジョンソンも、やがてはフォードのドライバーになるのだが、その時は本当に「身売り」するのかどうかで南部男たちの間で賭けが行われた、とまで言われている。
ムーンシャインのルーツをひもといていくと、18世紀にアパラチア山系に入植したスコットランド系アイルランド移民たちが始めたものらしい。穀物栽培に向かない痩せた土地だったため、人々はトウモロコシの栽培からウィスキー作りに転向したという。1791年に、ウィスキーに法外な税金が課せられ、これに猛反対する農民たちによって「ウィスキー一揆」が勃発。1万5000人の州軍隊によって鎮圧された。こうした歴史的背景から、大恐慌・禁酒法時代を経てアパラチア山脈一円はウィスキーの密造地帯となっていった。
最後に、色々調べていたら、「Junior Johnson's MIDNIGHT MOON」という名前のコーン・ウィスキーを発見。何とこれはジョンソン・ファミリーの密造酒のレシピを受け継いで作られているものだというのだ!もちろんジュニア・ジョンソンのお墨付きで。
日本にも輸入されているのだろうか・・・?こいつを一杯やりながら、『ラスト・アメリカン・ヒーロー』鑑賞、としゃれこみたいものだ。これぞ映画マニアの至福。クーッ!






