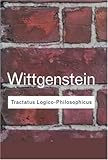スプーン一杯の重さが数トンになる超高密度の中性子星なるものがあるとな。カシオペア座かどっかに。本書はそんな感じの本なのではないか。薄い一冊なのにやたらと重い。独英併記版と
英語単独版があるが、前者はお高い。本書は後者。しかし
英語翻訳にウィトゲンシュタイン自身が立ち会っているので、
英語だけでもいいのではないのかと。
私はかつて速記に憧れ、速記習得がいかに大変かを知って怯み、ならば論理学記号をメモ取りに援用出来ないかとスケベ心を出す過程で論理学系の哲学者たちに出会ったのだった。「速記が出来る哲学者が妙に気になる」という意味不明の道筋を経ている。ウィトゲンシュタインは速記が出来る。個人ノートを速記で埋めた。クルト・ゲーデルも速記に馴染んでいる。速記達者な人間が言語(言語で思惟された世界)をどう捉えるか、おそらく私自身が多少はそういう目玉を持っていなくはないせいか、ごく漠然とではあるが見えるような感覚がある。問題はIQが大幅に足りないということと、ここまで変人じゃない、ということだが。
本書が物凄く読み難い理由の一つに、一般大衆は完璧に想定外というのがあるかと思う。おそらく数人程度の同僚(有名な論理学者たち)くらいしか読者として想定していない。熟練のパン職人が集まって、「水じゃない、ウォッカだ」「おお」「そう来るか」とかとかボソボソ会話していたとする。素人がその場にいたら話の中身は全く見えない。多分、本書はそういう本で、部外者向けの解説が綺麗に省かれている。本書の草稿を読んだラッセルが腰を抜かし、「哲学書には解説というものが必要なんだよ」と至極まともな忠告をしたらば、「それでは『詩』が失われる」と言ってウィトゲンシュタインは譲らなかったそうだ。うーむ、philosophical poetryか、poetic philosophyか。そもそもご本人の存在自体が詩的なのだと私は感じるが。
取り敢えず、最初の一言、「The world is all that is the case」は、西洋文学史に燦然と輝くオープニングだと思う。ゾクリとするくらいにカッコイイ。読み進むと、ごくたまに「ナルホド!」となる。なる瞬間が妙に誇らしい。「I am my world」と言われ、私も子供の頃に全く同じことを思ったことがあるなあ、と不思議な感じがする。「理解したら忘れろ(梯子を外せ)」という言葉もよく分かる。ウィトゲンシュタインにとって「理解」とはすなわち「execution」なのだな。実行のあるところに、哲学は要らない。
とは言っても、大方はハラヒリ〜と過ぎて行く本だ。ただ終盤の五頁で倫理学と美学について語り出されるので、ジワリと感動が来る。最後に「What we cannot speak about we must pass over in silence」というこれまた超有名な言葉が響き、じゃじゃーん、とドラマチックに終わる。
サール教授(米の有名な哲学者)はウィトゲンシュタインを「中欧の深遠なる神秘主義者」だと言っていた。「『論考』を読むと、ウィトゲンシュタインのように喋り、考えるようになる(そして妻に嫌がられる)」とも。ここで唱えられる「picture theory of language」より、『Philosophical Investigations』の「セオリー構築を忌避する哲学」の方が凄い可能性はあるが、読み物としての詩的パワーは圧倒的にこちら。ウィトゲンシュタインの頭の中身は、一等星の光を放って遠くを照らし出し、時代を超え、ご本人にとっては甚だ不本意なことに、現在に至るまで、哲学界の雇用創出に大いに貢献ている。ごく最近、スティーブン・ピンカーが「現代哲学は言語に拘り過ぎる。人間は言語のみで思考するのではない」と言っておられたが、「The limits of my language are the limits of my world」という本書の言葉への返答にもなっている。
所詮は論理学が身についていない人間の感想なので、眉唾ということで。本書を専門的に理解したい方は、カントール、フレーゲ、ラッセルとメタ数学の歴史を辿ることになるのかな。そんな根性も頭脳もない私は、長い旅路にグッドラックと申し上げたい。