
小澤征爾 / マルタ・アルゲリッチ [DVD]
オザワとアルゲリッチの掛け合いが素晴らしいです。
アルゲリッチの力強く魅力的な響きと、小澤征爾のアンサンブルに込められた哲学が絶妙に融合し、トータルとして、大変素晴らしい音楽が作り上げられています。是非一度聞いて見て下さい。 
小澤征爾さんと、音楽について話をする
村上春樹氏の音楽関連本は、これまで上梓されたものは、ほぼ漏れなく手にして愛読してきたが、今回は巨匠小澤征爾氏とがっぷり四つに組んだ、クラシック談義。ちょっと敷居が高いかなとは思ったが、いざ読み出してみると、小澤氏の飾らない人柄と、村上氏の巧みな聞き上手振りが、うまい具合にかみ合っていて、止まらず最後まで読み通してしまった。
大半は村上氏の個人オフィスで、村上氏が集めた小澤氏のレコードを聞きながら、時にお茶やおにぎりを口にするなどとてもリラックスしたなかで、これまでの小澤氏の数々のオーケストラでの経験談や、演奏に関する見解、様々な著名人との交流など興味深い話が、零れるように披露されてゆく。 そんな中で意外だったのは、小澤氏が自分の過去の演奏をほとんど聞いていないという事実だ。驚いたことに、学生時代いかに貧しかったとは言え、レコードもそれを再生するステレオすらも持たずに、ただスコアばかり読んでいたと言うのである。またあれだけ時間を掛けてオペラ作品のリハーサルを重ね、舞台で長時間演奏するくせに、いざ鑑賞する立場になると、オペラは長すぎて、ほんのさわりしか聞かずに帰ってしまう事が多い、というのだ。 それともう一つ、英語やドイツ語があまり出来なくて、アシスタント指揮者時代バーンスタインの貴重な話をほとんど理解できなかったり、新聞に載った自分の演奏の批評を余り読めなかった、という述懐だ。 これらの楽屋話を通して感じたのは、クラシック音楽の製作過程も一つの『仕事』なのであり、天才小澤征爾も、決して霞を食って生きる「雲の上の存在」なのではなく、公演に合わせて早朝から楽譜を読み込み、リハーサルに汗を流す生身の人間だ、ということだ。 それにしても何と純で、無垢な魂であることか。この魂が、ひた向きに音楽の製作に取り組む姿が、私に言い知れぬ畏敬の念と羨望の思いを抱かせる。 スイスはレマン湖畔で催された、若手弦楽奏者を集めての小澤アカデミーでのセミナーの模様を伝える村上氏の短報も、音楽に携わる若者とベテランの真摯な音楽への取り組みの姿が活写されており、長い対談をはさんでの良いアクセントになっている。 この本を通じて、クラシックが大変身近なものに感じられるようになった。 なお、小澤氏によるあとがきが、短いながらその真率な人柄がにじみ出ていて、プロの書き手である村上春樹氏のものとはまた違った意味で、心に響くものを感じた(H23.12.25)。 
オーケストラがやって来た DVD-BOX
懐かしき「オーケストラがやって来た」の番組の一部をまとめたDVDです。
今 音楽を学んでいる学生さんは このDVDを視聴されたほうが良いです。 どうやって、如何にして 音楽を演奏していくか、、、昨今、コピペ社会、人工加工社会が無かった文化も科学技術も成長しつつ時代の歴史的記録と思ってください。きっと、何か 得るところが多い DVDです。 
音楽 新潮文庫
クラシック音楽をより深く理解したい人や、指揮者を目指している人などには、すごく参考になる良い本だと思います。
内容は少し難しい部分もありますが、小澤氏と武満氏の対談形式で進むのでわりとサラッと読めます。 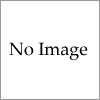
春の祭典 [DVD]
春の祭典は演奏する側にとって、大変難しい曲であるが、小澤征爾の構成感のある、それでいて感情があふれんばかりの、熱い演奏が聞ける一枚である。小澤征爾の指揮もたっぷり見ることができ、その繊細さと的確さに、非常に心打たれるものがある。是非、おすすめしたい。
|

上原カエラkaera -002 
インプラントインプラント治療 インプラントのメリット・デメリット 
マッサージ器最強のマッサージ機買ってみた!パナソニック つかみたたきAuto! 
那覇那覇 弾丸一人旅 2013正月 
NEW:Z100% Pure New Zealand 
渡辺純子渡辺順子のワインテイスティング vol25. 恐るべし日本ワイン 
Hi-TOUCH RookiesHi-TOUCH Rookies You -something beautiful- ![Fuyumi Soryo // Boyfriend OVA - End [ボーイフレンド ED] 惣領冬実](http://img.youtube.com/vi/KlcyzYGksdc/2.jpg)
惣領冬実Fuyumi Soryo // Boyfriend OVA - End [ボーイフレンド ED] |
[動画|ゲーム|ヤフオク]
[便利|辞書|交通]
[ランキング|天気|メル友]
[占い|住まい|ギャンブル]
【ひよこストライク!】ヒマリさんコメント
2 JUN 2013 都市対抗野球北関東大会 日立製作所チャンステーマ
小澤征爾 ウェブ

